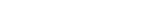「軍事支出の傾向と課題」に関するパネルディスカッションの開催
2013年4月15日
|
4月15日、日本政府国連代表部は、国連軍縮部とストックホルム国際平和研究所(SIPRI)と協力して、国連本部において、世界各地の安全保障環境などが、どのように各国の軍事支出や予算に影響を与えているかについて議論するパネルディスカッションを開催しました。この会合は、SIPRIが2012年の世界の軍事支出に関する報告書を同じ日に公表したこと、また、国連本部において、国連軍縮委員会の審議が4月1日から19日の予定で開催されていることにも合わせて開催されました。
会合においては冒頭、国連軍縮担当次席上級代表のガンバ氏が、参加者に歓迎の言葉を述べるとともに、SIPRIのデータが国連加盟国が行っている軍事支出に関する公式な報告を補完する上で重要な役割を果たしていると評価しました。引き続き西田国連大使が、日本が国連における軍事支出を巡る議論を重視していることを説明し、国連における議論は、各国間の透明性を高め、信頼醸成に寄与すると述べました。また、西田大使は、冷戦後、軍事支出の傾向に変化が見られ、それまで支出が多くなかった、アジアを含む各地域において大幅な増大が見られることを指摘しました。西田大使は、この分野において、NGOやシンクタンクを含む非政府組織が重要な役割を担っている旨述べました。
引き続いて行われた、パネルディスカッションにおいては、3名のパネリストが発言しました。まずSIPRIのソルマリノ上級研究員が、2012年のデータの内容を説明し、同年の世界の軍事支出は前年比で減少に転じたことを説明しました。世界の軍事支出の総計が1.75兆ドルに上り、これが世界全体のGDPの2.5%を占めている一方、この額は冷戦終了後も引き続き高い水準で推移している旨指摘しました。この減少は、米国、EU諸国及び他の西側諸国が直面している財政問題に起因していると述べる一方、ロシア、中国、サウジ・アラビアをはじめとする他の国々の軍事支出の増加によって、全体としての減少額は減殺されていると説明。ソルマリノ氏は、一部の関係者は今年の軍事支出の傾向について、「西側からその他の地域へ」の移行と説明していると述べました。 (SIPRIによる2012年の軍事支出のデータはこちらをご覧下さい。)
国連軍縮部のプリンツ通常兵器課長は、国連決議に基づき各国が行っている軍事支出に関する通報は、通報そのものを目的とすべきではなく、各国間の対話を促進するために行われるべきであると述べました。また、ニューヨーク大学のシドゥ博士は、軍事支出と軍事同盟の関係、あるいは最近採択された武器貿易条約(ATT)が軍事支出の今後の傾向にどのような影響を与え得るかといった、様々な論点を提起しました。
パネリストを交えての議論は、他の出席者を交えて続けられ、政策的な課題から軍事支出のデータ収集に関する技術的な質問まで多岐にわたりました。参加者の中からは、対人地雷禁止条約やクラスター弾条約といった軍縮関連条約が、軍事支出にどのような影響を与えるかといった質問や、ATTや包括的核実験禁止条約(CTBT)についても、軍事支出の抑制に一定の効果を有するのではないかという指摘もなされました。ほかにも、技術革新が軍事支出を削減する上で何らかの役割を果たすか否かについての疑問も提起されました。
この会合は、国連加盟国、NGO及びその他の関係者が、SIPRIの最新のデータを通じて、軍事支出に関する最近の傾向や軍縮の目標に関して議論をする有益な場となりました。日本は今後も、国連において軍事支出に関する透明性の向上と、対話の促進の重要性を訴えるとともに、国連での議論に積極的に関与していきます。 |
パネル・ディスカッションの模様。立ち見が出るほどの盛況でした。
国連軍縮担当次席上級代表のガンバ氏(右)が挨拶。司会はSIPRIのデ・ヨング・ウドラ氏(右から3人目)
西田国連大使が冒頭発言。軍備支出の透明性向上を重視する日本の考えを説明。
SIPRIのソルミラノ上級研究員(中央)が2012年の統計の内容を解説。
ニューヨーク大学のシドゥ博士(中央)が、最近の軍事支出の傾向を踏まえた論点を提起。 |