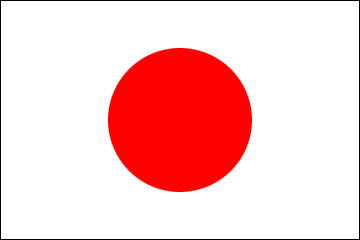秋田美央 二等書記官 「ジェンダー平等と女性のエンパワメントに向けた国連加盟国の役割」
令和5年8月30日
はじめに
2020年8月末から当代表部社会部でジェンダーの担当官として勤務しております。
私は外部からの任用(任期付職員)で、以前は国連や外務省本省、NGO等で国際協力、開発関係の仕事をしておりました。現在は主にジェンダーの分野における国連加盟国間交渉・調整、国連機関のドナー担当者としての役割を担っています。

私は外部からの任用(任期付職員)で、以前は国連や外務省本省、NGO等で国際協力、開発関係の仕事をしておりました。現在は主にジェンダーの分野における国連加盟国間交渉・調整、国連機関のドナー担当者としての役割を担っています。

2023年2月 UN Women執行理事会
国連におけるジェンダー
ジェンダー平等と女性のエンパワメントは国連で扱う全ての案件に関係があると言っても過言ではなく、国連総会、第3委員会、安全保障理事会(安保理)、経済社会理事会、国連女性の地位委員会(CSW)等、あらゆる会議で扱われ、また、本分野に特化した機関(国連女性機関=UN Women)もあります。
1 加盟国交渉 ―思いは同じでも、文言交渉は数十時間に-
国連の様々な会合体には成果文書があり、国連加盟国が国連としての意思を表明する文書は決議(resolution)と呼ばれます。国際連合はUnited Nationsという名のとおり、Nation(加盟国)の連合ですが、簡単にはuniteできないのが実情です。特に、ジェンダーの分野は各国の文化、宗教、社会的慣習と言った、理屈では説明できない要素が大きく関係しているため、加盟国間協議は平行線をたどり、最後まで合意できず、投票に持ち込まれることも多々あります。国連総会第3委員会(社会、人道、人権分野)では例年、「女性・女児に対する暴力撲滅」「FGM(女性性器切除)撲滅」「フィスチュラ(産科ろうこう)」撲滅」等の複数の決議を協議し、採択しています。国連全体として、これらの問題を解決したいという思いは皆、一緒なのですが、その思いを訴える決議の文面において合意をみられないことがしばしばあります。例えば、SDGs5(ジェンダー)の統計上の指標にも使われている「intimate partner violence(親密なパートナー間の暴力)」という言葉を巡っても、そのような概念は自国に存在しないと言って反対する国、このような個別の概念を入れ込むべきであるとして強く推進する国が対立しています。例年3月に開催され、女性の世界の国連総会とも呼ばれる女性の地位委員会(CSW)でも成果文書の交渉が約1月間行われるのですが、毎年、深夜、早朝まで加盟国間で協議を続けています。
2 決議の先にあるのは人
残念ながらこのように国連加盟国が分断しがちな本分野において、日本は特定の文言、イデオロギーを推すのではなく、国連加盟国全体として合意に至ることが重要との信念の下、日夜、議論に参加しております。なぜならば、本分野において究極的に最も大事なことは、細かい表現ぶりではなく、各国が賛同できる決意文書を作成し、それを基に各国が主体的にジェンダー平等に向けた政策立案や施策を実施していくことだと考えるからです。
このような日本の姿勢は中立的でバランスが取れているとして、国連で協働するパートナーに、他の加盟国から選ばれることもよくあります。2022年、日本はアフリカのシエラレオネと共に、国連初の性的暴力に関する総会決議である「性的暴力被害者の司法アクセス等に関する決議」(A/RES/76/304)のファシリテーターを務めました。この際も、日本の日頃の姿勢を評価してくれたシエラレオネから一緒にやってもらえないかとの依頼がありました。新たな決議案を一から作成するのは非常に骨の折れる作業で、準備段階から採択まで1年以上、加盟国間でも何ヶ月も協議を重ねました。私は現在の役職に就く直前は、アフリカのマラウイの村で女性たちとござの上に座り、鶏が駆け回る中、家族計画を普及する仕事をしていたので、国連で決議の文言交渉をしていると、物事が起きている現場から遠いなという気持ちになることもありました。しかし、第76回総会で本決議がコンセンサス採択された際に、議場に来ていた性的暴力被害者の団体の人たちが涙を流して喜んでいたのを見た時は、常に、決議の先にある、世界中の一人一人の人のことを考えて臨まなければならないと改めて考えさせられました。

2022年9月 国連総会決議採択後、シエラレオネ代表部と
3 安保理理事国、ドナー国としての日本
2023年1月から日本は安保理の非常任理事国になりました。安保理にも女性・平和・安全保障という女性関連の議題があります(詳しくはhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/pc/page1w_000128.html)。紛争予防・解決プロセスなどにおける女性の参画及び紛争下での女性の保護・権利等について安保理の様々な会合で議論を進めています。安保理は国連加盟国の中でも限られた15カ国の理事国だけが全ての議論に参加することのできる特別な場所です。特に各国を代表して選挙で選ばれた非常任理事国としての大きな責任を感じながら、日々、どのように女性・平和・安全保障アジェンダを実効力のあるものにできるか考えながら仕事をしています。
また、国連の現場での活動を担うUN Women等の国連機関には執行理事会という、選挙で選出された理事国と、その他の国連加盟国が機関の運営について話し合う民間企業の株主総会のような会合があります。理事国にはUN Womenに資金を拠出している国や、UN Womenがプログラムを実施する国等、様々な立場の国が含まれます。日本はドナー国として、資金の使途や活動が適正で効果のあるものであるか等、厳しく精査し、他国と連携しながらUN Womenへの支援をしています。
1 加盟国交渉 ―思いは同じでも、文言交渉は数十時間に-
国連の様々な会合体には成果文書があり、国連加盟国が国連としての意思を表明する文書は決議(resolution)と呼ばれます。国際連合はUnited Nationsという名のとおり、Nation(加盟国)の連合ですが、簡単にはuniteできないのが実情です。特に、ジェンダーの分野は各国の文化、宗教、社会的慣習と言った、理屈では説明できない要素が大きく関係しているため、加盟国間協議は平行線をたどり、最後まで合意できず、投票に持ち込まれることも多々あります。国連総会第3委員会(社会、人道、人権分野)では例年、「女性・女児に対する暴力撲滅」「FGM(女性性器切除)撲滅」「フィスチュラ(産科ろうこう)」撲滅」等の複数の決議を協議し、採択しています。国連全体として、これらの問題を解決したいという思いは皆、一緒なのですが、その思いを訴える決議の文面において合意をみられないことがしばしばあります。例えば、SDGs5(ジェンダー)の統計上の指標にも使われている「intimate partner violence(親密なパートナー間の暴力)」という言葉を巡っても、そのような概念は自国に存在しないと言って反対する国、このような個別の概念を入れ込むべきであるとして強く推進する国が対立しています。例年3月に開催され、女性の世界の国連総会とも呼ばれる女性の地位委員会(CSW)でも成果文書の交渉が約1月間行われるのですが、毎年、深夜、早朝まで加盟国間で協議を続けています。
 2022年の国連第3委員会 |
 2023年3月、女性の地位委員会における深夜の文言交渉の様子 |
2 決議の先にあるのは人
残念ながらこのように国連加盟国が分断しがちな本分野において、日本は特定の文言、イデオロギーを推すのではなく、国連加盟国全体として合意に至ることが重要との信念の下、日夜、議論に参加しております。なぜならば、本分野において究極的に最も大事なことは、細かい表現ぶりではなく、各国が賛同できる決意文書を作成し、それを基に各国が主体的にジェンダー平等に向けた政策立案や施策を実施していくことだと考えるからです。
このような日本の姿勢は中立的でバランスが取れているとして、国連で協働するパートナーに、他の加盟国から選ばれることもよくあります。2022年、日本はアフリカのシエラレオネと共に、国連初の性的暴力に関する総会決議である「性的暴力被害者の司法アクセス等に関する決議」(A/RES/76/304)のファシリテーターを務めました。この際も、日本の日頃の姿勢を評価してくれたシエラレオネから一緒にやってもらえないかとの依頼がありました。新たな決議案を一から作成するのは非常に骨の折れる作業で、準備段階から採択まで1年以上、加盟国間でも何ヶ月も協議を重ねました。私は現在の役職に就く直前は、アフリカのマラウイの村で女性たちとござの上に座り、鶏が駆け回る中、家族計画を普及する仕事をしていたので、国連で決議の文言交渉をしていると、物事が起きている現場から遠いなという気持ちになることもありました。しかし、第76回総会で本決議がコンセンサス採択された際に、議場に来ていた性的暴力被害者の団体の人たちが涙を流して喜んでいたのを見た時は、常に、決議の先にある、世界中の一人一人の人のことを考えて臨まなければならないと改めて考えさせられました。

2022年9月 国連総会決議採択後、シエラレオネ代表部と
2023年1月から日本は安保理の非常任理事国になりました。安保理にも女性・平和・安全保障という女性関連の議題があります(詳しくはhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/pc/page1w_000128.html)。紛争予防・解決プロセスなどにおける女性の参画及び紛争下での女性の保護・権利等について安保理の様々な会合で議論を進めています。安保理は国連加盟国の中でも限られた15カ国の理事国だけが全ての議論に参加することのできる特別な場所です。特に各国を代表して選挙で選ばれた非常任理事国としての大きな責任を感じながら、日々、どのように女性・平和・安全保障アジェンダを実効力のあるものにできるか考えながら仕事をしています。
また、国連の現場での活動を担うUN Women等の国連機関には執行理事会という、選挙で選出された理事国と、その他の国連加盟国が機関の運営について話し合う民間企業の株主総会のような会合があります。理事国にはUN Womenに資金を拠出している国や、UN Womenがプログラムを実施する国等、様々な立場の国が含まれます。日本はドナー国として、資金の使途や活動が適正で効果のあるものであるか等、厳しく精査し、他国と連携しながらUN Womenへの支援をしています。
最後に
国連において、ステートメントや会合での発言をする際は、常に、世界から見られていることを意識して、日本外交、ODA、国内施策の様々な活動を紹介しています。日本人は控えめだとよく言われますが、国連では、各国の記憶に残ることを意識してアピールをするよう心がけています。日本国民を代表して現在の仕事をさせて頂いているので、今後も日本の外交、公益、そして世界の公益、ジェンダー平等の実現を常に考えながら動いていきたいと思います。